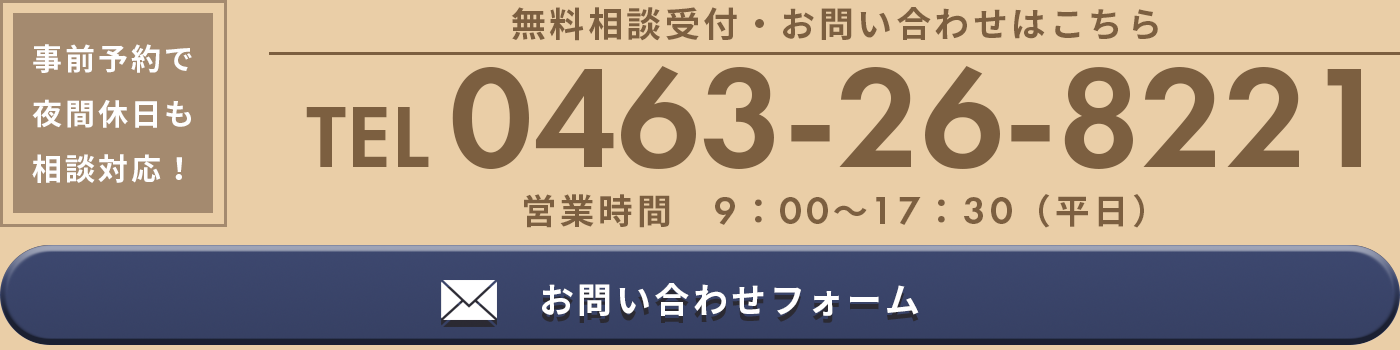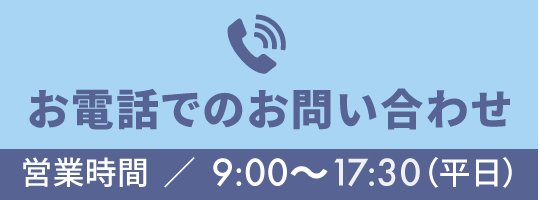コラム
相続(贈与)税 / ワンポイント
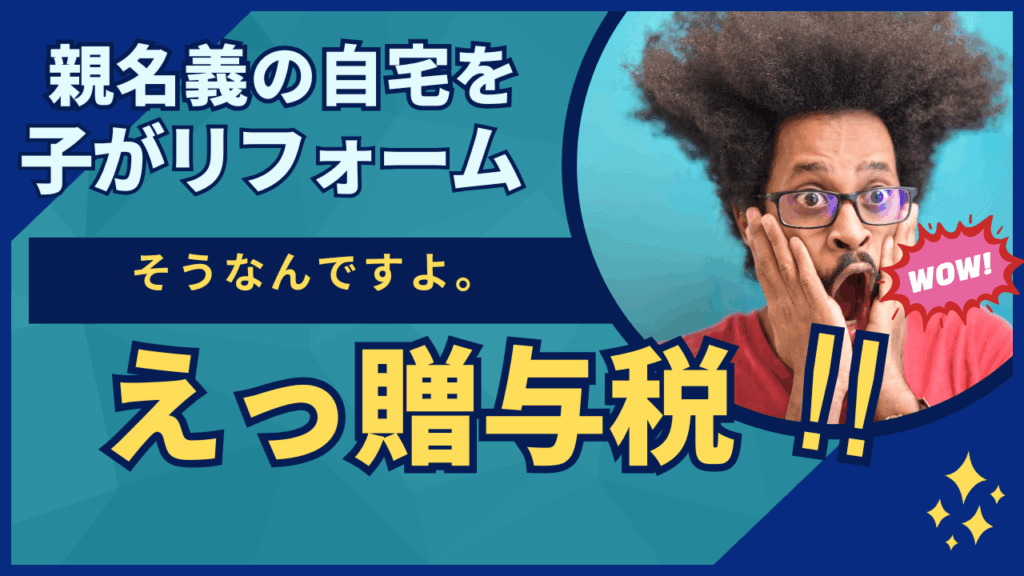
親の自宅を子がリフォームした時の課税
親の自宅をリフォームするときに、子が工事代金を負担すると、建物は親の所有物であるため、贈与税が課税されます。
リフォーム部分の所有権は親に帰属する
民法には不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する取扱いがあります。「従として付合した」というのは、不動産に付着しているものをいい、子が工事代金を負担したリフォーム部分は建物本体に付着しており、分けることはできないので、そのまま親の所有物となって贈与関係が発生することになります。
子の受けた損失を建物の持分で代物弁済
しかし、贈与課税を発生させない方法があります。親が負担すべき工事代金を子が負担したにもかかわらず、リフォーム部分の所有権は親のものとなったのですから、子は自身の受けた損失に見合う償金を親に請求することができます。
一方、親にリフォーム工事代金を支払う資金がない場合は、子の償還請求に対し、工事代金の支払債務の返済を金銭の代わりに建物所有権の持分を子に代物弁済として移転させます。この場合、代物弁済を受けることについて、債権者である子の承諾が必要になります。
代物弁済には譲渡所得税が課税される
代物弁済は譲渡所得の対象となる資産の譲渡として扱われるので、譲渡所得税の課税対象となります。代物弁済により消滅する債務金額を収入金額とし、建物の取得価額を控除した残額が譲渡所得となります。
そこで代物弁済により消滅する債務金額と等価となる建物持分を子に移転させることによって、譲渡所得がゼロとなり、課税を回避することができます、例えば、リフォーム前の建物時価を300万円、リフォーム工事代金を1,200万円、リフォーム後の建物持分の移転割合を80%(1,200万円÷(300万円+1,200万円))に設定すると、譲渡所得はゼロとなり、課税されません。
収入金額=代物弁済する債務額1,200万円
取得費=(300万円+1,200万円)×80%=1,200万円
譲渡所得金額=収入金額-取得費=ゼロ(短期譲渡・長期譲渡ごとに区分計算する)
リフォーム前に親から建物の贈与または譲渡を受けておくことも可能です。
なお、居住用財産を他の者と共有とするための譲渡、親子間の譲渡には、3,000万円控除や軽減税率の特例は適用されません。
2025年11月15日

相続税と所得税の二重課税
相続で取得した財産について相続税が課された後、同じ財産に所得税が課されると二重課税となって所得税の非課税規定が適用される場合があります。
二重課税を排除した長崎年金訴訟
相続税と所得税の二重課税を認めたのが平成22年の長崎年金訴訟です。最高裁では相続で取得した定期金給付契約により将来にわたり受け取る保険金の現在価値に課された相続税と、取得した保険金の元本部分に課された所得税が二重課税になるとした上で所得税の非課税規定が適用されました。
所得税の課税根拠は包括的所得概念
所得税が課税される根拠は、包括的所得概念と呼ばれるものです。金子宏教授「租税法」によれば、包括的所得概念とは、人の担税力を増加させる経済的利得が、すべて所得を構成すると考えます。一時的・偶発的・恩恵的利得も所得の範囲に含まれ、債務免除益のほか、現物給付、為替差益などの経済的利益にも課税され、不法な手段による利得も納税者が管理支配しており、課税の対象となります。
所得税の非課税規定
相続税及び贈与税は相続、贈与、遺贈により取得した財産の経済的価値に担税力を認めて課税されますが、相続財産、贈与財産の経済的価値と同一の経済的価値に対しては所得税を二重に課税しないとするのが所得税の非課税規定の考え方です。
譲渡所得に二重課税は生じない
相続で取得した土地を譲渡した場合、相続財産に課された相続税と被相続人の保有期間中に生じた土地の含み益が譲渡により実現して課された譲渡所得税は二重課税となりません。判例では相続により取得した土地と被相続人の土地保有期間中のキャピタルゲインに同一の経済的価値に対する二重課税が行われることを認めていません。
債務免除益に二重課税は生じるか?
被相続人の借入金について一定金額を期日までに弁済すれば残額を免除するという停止条件付債務を承継した相続人が、相続の後に受けた債務免除益について所得税が課されたため、相続税と所得税の二重課税が争われた裁判があります。一審は、債務免除を受けた時点が相続開始の後で二重課税ではないとしましたが、控訴審は、債務免除による経済的利益は相続開始の時に実質的に生じており、二重課税になるとして非課税規定の適用を認めました。課税庁は最高裁に上告しています。
2025年11月1日
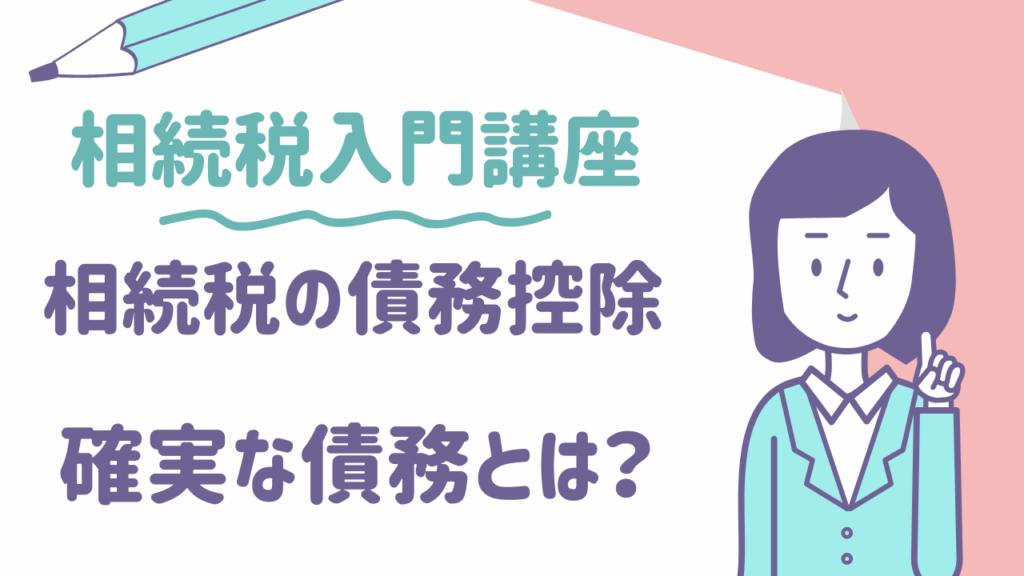
相続税の債務控除『確実な債務』
相続税の申告では被相続人の債務は相続財産から控除されます。この場合、控除される債務は「確実な債務」に限るとされています。被相続人の借入金は控除される債務の代表例ですが、その債務が相続の後に債務免除の対象となっていた場合、債務控除できるのでしょうか。
確実な債務の要件
債務控除を受けるためには、債務が存在していること、及び債権者より債務弁済の履行が義務づけられていることが要件とされており、この要件を満たす債務を「確実な債務」と呼んでいます。
債務免除は担税力を減殺しない
相続税は財産を取得した相続人に担税力を認めて課税されます。また、被相続人の借入金は相続財産から弁済して担税力が減殺されるので遺産総額から債務額を控除することになります。しかし、その債務が免除されることが確実とされる場合、担税力は減殺されないので債務控除は認められないことになります。
債務免除に停止条件がある場合
被相続人の借入金のうち一定金額を期日までに弁済すれば、残額は弁済を免除する停止条件が借入契約に付されていた場合、その成就がほぼ確実であると見込まれるときは債務控除を認めない判例があります。
しかし、被相続人の死亡時に債務免除に必要な弁済が未達であれば、相続人に弁済の履行義務はあるので、残債務は「確実な債務」と言えるのではないでしょうか。
債務免除は確実な債務でないとされた裁判
実際の裁判事例です。相続人は被相続人の16億円の借入債務を引き継ぎ、銀行との和解による債務免除に必要な金額を弁済して残額約9億円の免除を受けました。そして相続税の申告では相続開始時に債務免除を受けることは確実であったとして約9億円の残債務について債務控除せず、増加した純資産額に対する相続税を負担しました。ところが債務免除益にも所得税が課税されて二重課税となったため、相続人は所得税の非課税を求めて訴訟を起こしました。
一審、二審では相続人の資産状況から債務免除に必要な分割金は優に支払うことができ、残債務9億円は「確実な債務」でなかったとされました。しかし、相続人が仮に相続時に停止条件が成就していなかったことを理由に債務免除部分の債務を「確実な債務」として申告していた場合、裁判は同じ展開になったのか疑問が残ります。
2025年10月13日
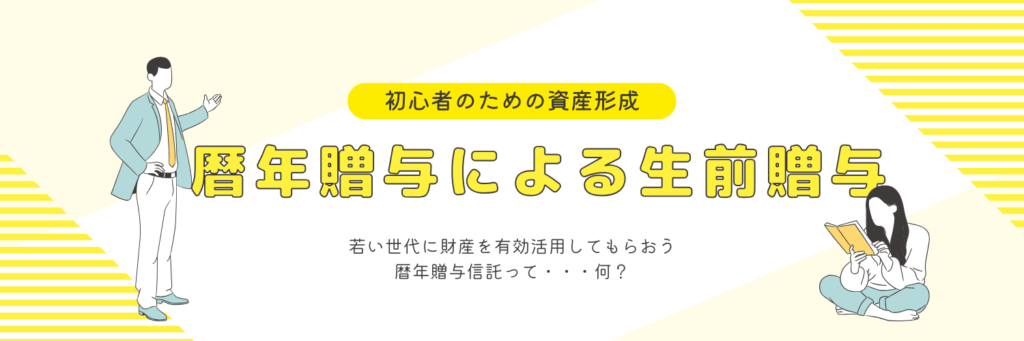
暦年贈与信託による生前贈与
生前贈与は相続財産を減らせることに加え、子や孫の若い世代に相続前から財産を有効に活かしてもらうことができます。
生前贈与加算期間は7年以内に延長
暦年贈与は毎年110万円まで基礎控除を受けられます。令和6年1月1日以後の贈与について相続税の課税価格に加算される生前贈与は、相続開始前7年以内(改正前は3年以内)の贈与となりました。ただし、令和8年12月31日までの贈与の加算対象期間は3年間に据え置かれ、以後、毎年1年ずつ延長されて、令和13年1月1日の贈与から7年間となります。
また、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額について、総額100万円まで加算対象外となります。
暦年贈与信託を生前贈与に活用
暦年贈与に信託銀行が扱う暦年贈与信託を利用することもできます。贈与者は金銭信託で委託者兼受益者となり、信託銀行は受託者となって、毎年、贈与を受ける親族、贈与時期、贈与金額を決めると信託銀行が贈与の手続きを贈与者、受贈者に取り次いでくれます。贈与者はあらかじめ贈与したい複数の親族を候補者として選定しておき、普段は信託財産として運用益を受益者として享受し、贈与のときは、毎年、候補者の中から贈与したい相手の親族を選び、贈与したい金額を決めます。信託銀行は書面で贈与者と受贈者の意思の合致を確認した後、信託財産から贈与する金額を送金します。
贈与税は基礎控除額110万円を控除した額に課されます。信託銀行の取扱商品によっては、贈与者が受益者のまま贈与するもの、贈与時に受益者を受贈者に変更して贈与とするものもあるようです。
連年贈与、定額贈与には注意!
暦年贈与で毎年、定額の贈与を継続した場合、贈与額の合計額について課税リスクが生じます。国税庁は、例示として毎年100万円ずつ10年間の贈与があらかじめ当事者間で約束があり、贈与が定期金給付契約の締結によるものとされた場合、契約した年に贈与額全体について贈与税を課すとしています。暦年贈与信託では、毎年、受贈者を候補者から選定し、贈与の有無、贈与額を決めることができますが、贈与の際は贈与課税について注意が必要です。
また、贈与には子や孫に資産を早期に移転することで、その生活スタイルを贈与に依存させてしまう側面もあることにも留意しましょう。
2025年9月23日
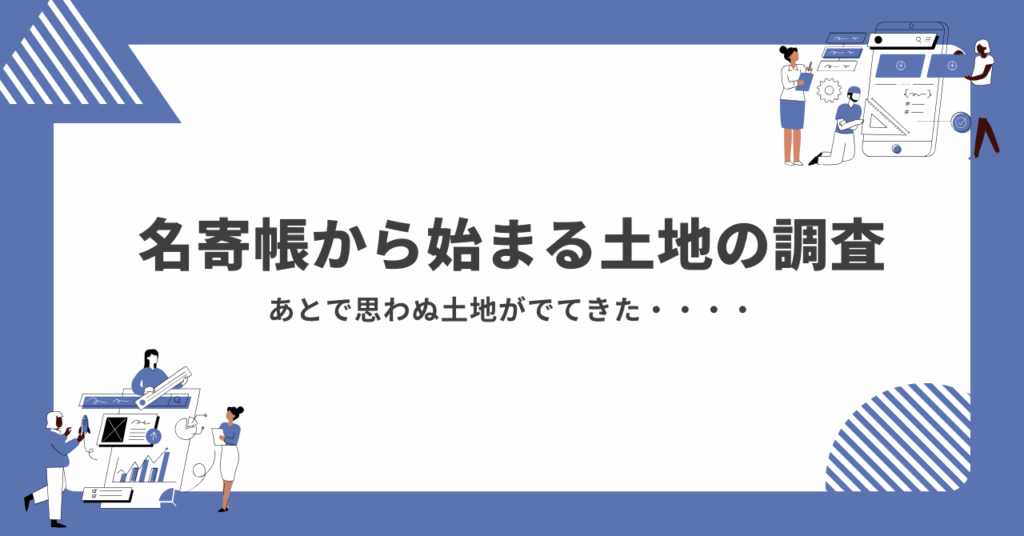
名寄帳から始まる土地の調査
相続の際、固定資産税課税明細書に記載の土地・建物が相続財産だと思っていたら、あとで思わぬ土地が出てきて戸惑うことがあります。
名寄帳で所有土地を確認
固定資産税課税明細書に記載がない土地は、固定資産税がかからない非課税の土地です。多くは私道や公衆用道路です。
非課税の土地の調査は、市区町村の資産税課などの窓口で名寄帳(固定資産課税台帳の土地・建物を所有者ごとに表示したもの)を取得することにより、相続のあった年の1月1日時点で登記されている被相続人名義の土地を確認することができます。
ただし、その年、1月1日より後に取得した土地は表示されません。また、他の市区町村にある土地も表示されません。もし、被相続人の居宅や貸金庫に覚えのない売買契約書や登記済証があれば、その地番を手掛かりに現在の登記名義人が誰かを確認することで相続財産となるかが判明します。既に譲渡済みの場合もあります。
利用価値のない土地の処分
非課税の宅地は、被相続人の所有する建物への通路として利用しているような場合を除き、財産上の価値はほとんど見込めず、相続では望まれない財産となることが多いと思われます。
そのような土地も相続人の誰かが引き継がなければなりません。しかし、相続人が共有で相続することは将来の処分を更に困難にしてしまうので、お勧めできません。そのような場合は隣地の地権者に買い取ってもらうか、隣地の地権者の所有土地と共同で売却するなどの方法を検討することになるものと思われます。
土地区画整理事業で道路に提供される場合
土地区画整理事業が施行中の地区において、公衆用道路として使用されている私道が換地処分後、市区町村に道路用地として譲渡される予定の場合、相続開始時は事業完了前のため、登記簿上、被相続人名義の土地のままとなっていることがあります。
このような土地には換地が定められず、換地不交付申出により、市区町村から交付される清算金は譲渡所得の対象となります。この場合、優良住宅地の造成等のために国等に土地等を譲渡する場合の長期譲渡所得の課税の特例が適用され、2,000万円以下の長期譲渡所得金額についての税率は、所得税10%、住民税4%(通常は所得税15%、住民税5%)に軽減されます。
2025年8月28日
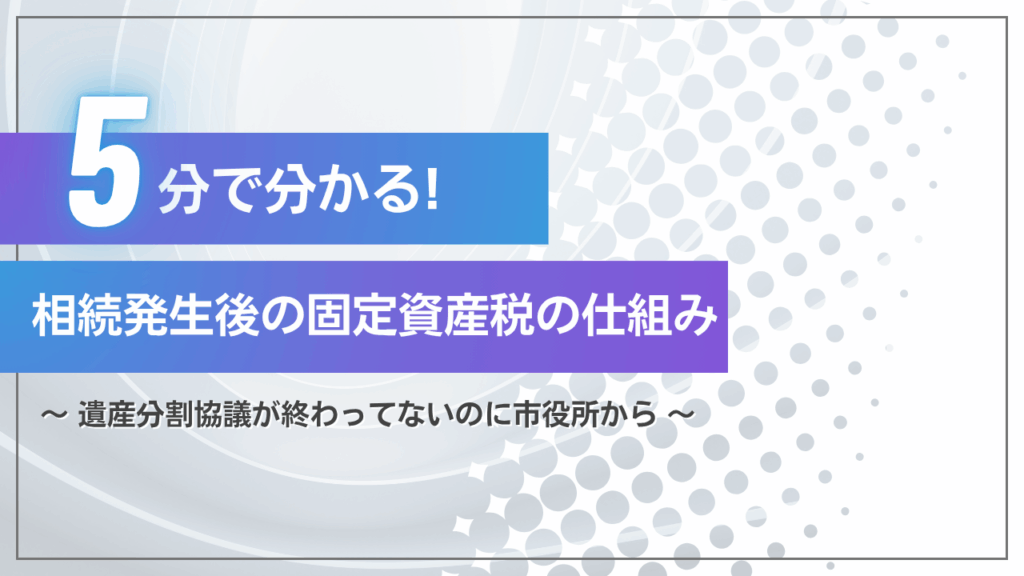
遺産分割協議が終わってないのに固定資産税の納付書が・・・・誰が払う?
土地・家屋の現所有者申告
遺産分割協議が終わらないうちに役所から固定資産税の案内が届くことがあります。これは土地や家屋を相続して新たに固定資産税を納付する人を役所に届け出るもので土地・家屋の現所有者申告と呼ばれます。
固定資産税の仕組み
固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に課される地方税です。市町村(東京23区は東京都、以下同)は不動産登記簿等に記載された土地・家屋の所有者に毎年5月頃、納税通知書を送付します。
固定資産税の評価額は地方税法に定める固定資産評価基準により、市町村が決定します。3年に一度、評価替えが行われ、直近では令和6年度に改定されています。
相続で納税義務も承継される
相続人は被相続人の土地・家屋取得に伴い、固定資産税の納付義務も承継します。市町村が現所有者申告の手続を求めるとき、現所有者は遺言や遺産分割協議で土地・建物を取得した者だけでなく、遺産分割協議前の法定相続人も該当します。
民法では相続があると、法律で定められた順番に相続人が決まり、法定相続分により財産・債務を承継します。したがって遺産分割前は相続人全員が現所有者となって固定資産税の納付義務を負うことになります。そして市町村は相続人の中から代表者を決めて、その者に納付してもらうこととしています。
現所有者申告書の提出期限は相続開始後3月とされており、具体的には市町村ごとの条例で決められています。届出書の様式も市町村ごとに定められており、ホームページに記載例が掲載されています。
現所有者申告書の添付書類には、相続人全員の戸籍謄本や住民票の提出を求める市町村や本人確認票(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示だけですむ市町村もあります。
相続人代表者が固定資産税を一度納付する
遺産分割協議前の固定資産税の納税義務は相続人全員にありますが、実務上は相続人代表者が一度納付し、後に相続人の間で各自の持分で精算します。土地・家屋の取得者の相続登記が行われると、以降は新しい所有者に納税通知書が送付され、共有の場合は引き続き代表者に送付されます。
なお、相続した不動産を売却したり抵当権を設定したりするためには相続登記(所有権移転登記)が必要となりますので忘れないようにしましょう。
2025年7月9日
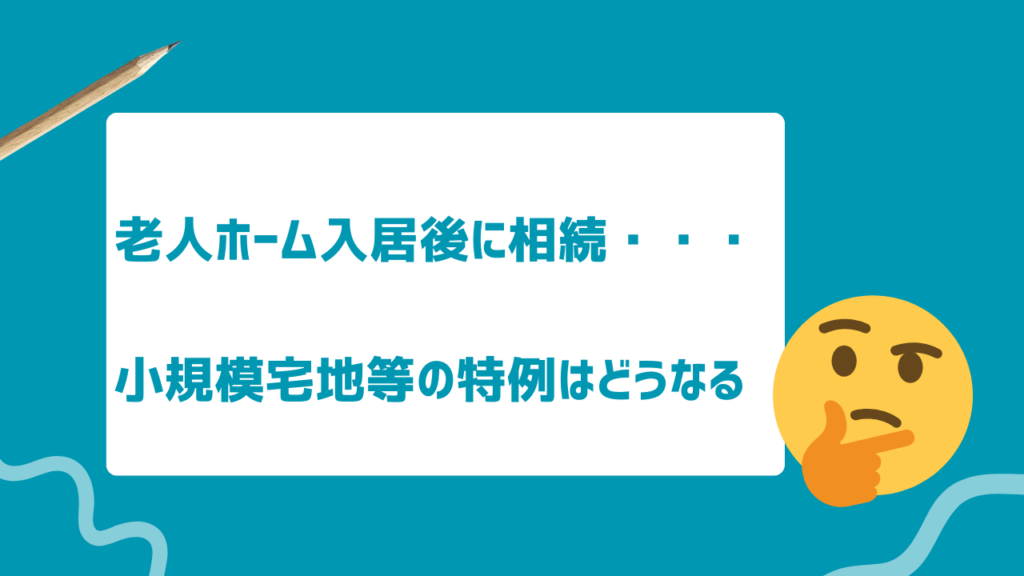
知らないと損する・・・?
小規模宅地等の特例 ~老人ホーム入居後に相続~
老人ホーム入居後に相続が発生した場合の小規模宅地等特例の適用可否
高齢化社会になり、親が老人ホームに入所するケースが増えており、寿命の内、健康寿命を超える要介護期間が、男性9~10年、女性12~13年程度とされているので、最近の傾向としては、介護が必要となってからの入所よりも、元気なうちから入所を決める傾向になっています。
それでは、老人ホームへ入居した後に相続が発生した場合の小規模宅地等の取扱いについて検討したいと思います。
居住用小規模宅地等の特例
平成25年度の税制改正において、老人ホームへの入所まで居住していた自宅の敷地に係る相続税の小規模宅地等の特例の適用について、一定の要件の下、その自宅の敷地は、相続開始直前における被相続人の居住供用宅地等の概念に該当することになる旨が法令に明記されました。
一定の要件とは、次の2つの要件です。
1.被相続人が要介護等認定者に該当(認定申請中に相続開始で事後認定も可)
2.入居老人ホームが老人福祉法等規定該当
都道府県知事への届け出が義務付けられいるため未届状態の老人ホームに入居してしまった場合には、小規模宅地等の特例は受けられなくなります。
無認可老人ホームへの入居は適用除外になりますので、入居時に必ず確認しましょう。
小規模宅地の取得者要件
宅地等の取得者ごとに係る要件もあります。具体的な判定としては、次の各場合には小規模宅地等の特例が使えます。
(1)配偶者が自宅に引続き居住の場合の配偶者が相続
(2)夫婦で老人ホーム入所後、留守宅の自宅を配偶者が相続
(3)被相続人が老人ホームに入所後、引続き居住をする同居親族が相続(生計一は要件ではない)
(4)(2)の物件を(3)の同居親族が相続
(5)(3)の引続き居住の同居親族が対象の自宅を建替えた後に引続き居住継続して相続
(6)被相続人が老人ホームに入所後、留守宅を別居の親族の「家なき子」が相続
なお、(3)の同居親族については、以下の3要件の具備が必要です。
1.相続開始直前に被相続人の居住用敷地に居住している
2.相続税の申告期限まで当該宅地等の所有継続
3.相続税の申告期限まで当該宅地等での居住継続
プラスアルファー
被相続人が老人ホームに入所後の留守宅に生計一親族が入居した場合は、要件不要で適用です。また、留守宅を賃貸した場合、特定居住用宅地等としての特例は使えませんが、貸付事業用宅地としての小規模宅地等の特例を使うことができます(3年以上の期間貸付けが条件)。
2025年6月28日
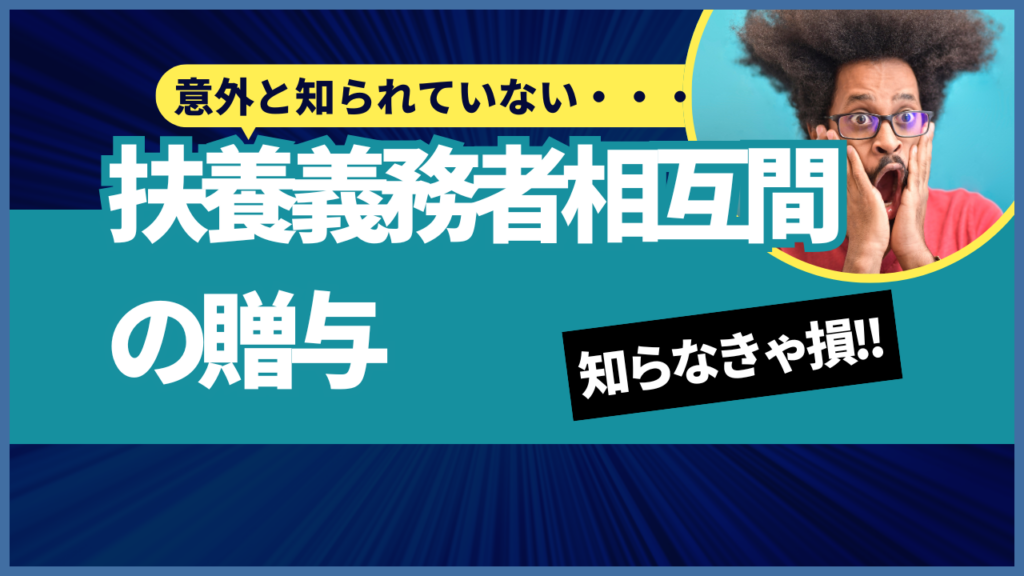
扶養義務者からの生活、教育費の贈与って・・・
新年度がスタートし、入学や進学に伴う学費など、まとまったお金が必要な時期ですね。
令和6年から生前贈与のルールが変わったことで、弊所でも贈与税の相談が増えている現状です。
学費といえば・・・・子・孫への教育資金の一括贈与非課税制度がありますが、
今回はもっとシンプルなお話です。
教育費資金の一括贈与非課税制度が気になる方はこちら
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
1.扶養義務者相互間での生活費または教育費の贈与は非課税。
扶養義務者相互間において生活費、教育費に充てるためした贈与により取得した金銭等で通常必要と認めるものは贈与税の非課税となります。
※要するに必要な時に必要な金額だけもらうということです。
例えば4年間分の大学の学費をまとめて一度に贈与する場合、贈与税の対象となる可能性が出てきます。また、教育費、生活費をもらい実際には使用せず、貯蓄、株式などの取得に充てている場合にも贈与税の課税対象となります。
※まとめて渡すのは要注意!!
毎年必要な都度、必要な金額をお渡ししましょう。(もらいましょう。)
2.生活費・教育費とは
ここでいう、「生活費」とは、通常の日常生活に必要な費用をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるものも含みます。
また、「教育費」とは、教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。修学旅行の費用も含まれます。
3.そもそも扶養義務者って・・・
相続税法に定める扶養義務者は民法上の扶養義務者です。
相続税法第1条の2第1号に定められており、「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
第1条の2《定義》関係|国税庁
「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」
の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A
4.相続税の申告にも・・・・扶養義務者。専門家に相談を
相続税の計算時に、未成年者控除、障害者控除を適用する場面があります。
該当する相続人から控除しきれない部分については扶養義務者から控除できます。
これを知らないと・・・相続税を多く納めてしまう結果に(涙)
経験豊富な専門家である税理士にご相談ください。
2025年4月7日
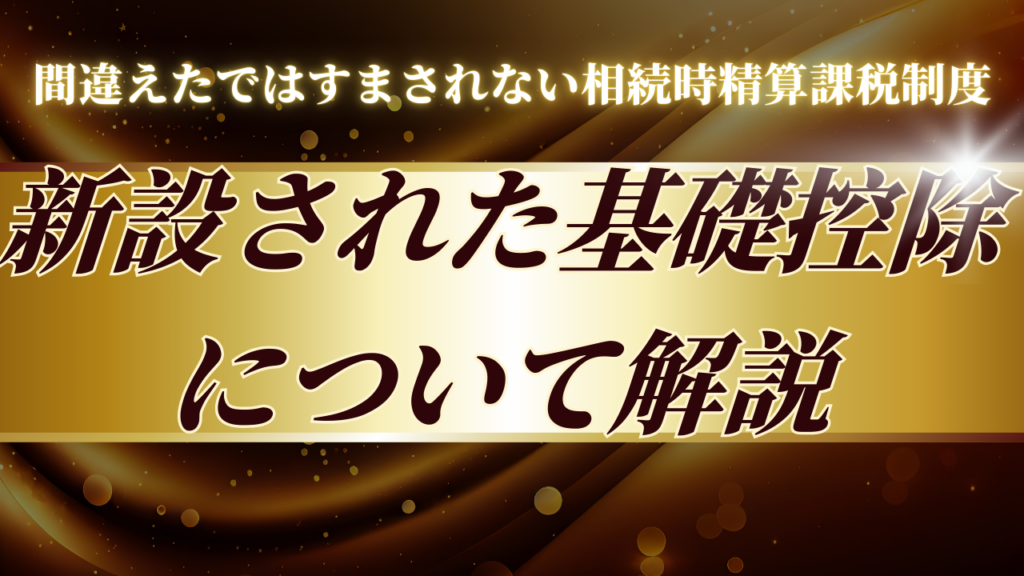
間違えたではすまされない、相続時精算課税制度!!
一度選択したら撤回できない相続時精算課税制度の基礎控除について解説
令和5年税制改正により創設された相続時精算課税制度における基礎控除について解説
大変申し訳ありません。相続時精算課税の概要については割愛しています。
相続時精算課税制度の基礎控除は、令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用されることになります。
■相続時精算課税制度(改正前)
(贈与税の課税価格-特別控除額)×20%
※特別控除額は2,500万円(既にこの規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)
つまり、一生涯で2,500万円です。
この特別控除額は、複数の特定贈与者(財産をあげる人)からの贈与受けた場合には
それぞれ2,500万円あります。
この特別控除額は期限内申告が絶対に必要です。
例えば、父と母の両方と相続時精算課税制度の贈与を選択した場合。
〇 父からの贈与について特別控除額2,500万円
〇 母からの贈与について特別控除額2,500万円
となります。
この考え方があるがゆえに間違えてしまう基礎控除110万円です。
※相続税の課税価格に加算する財産の価額:贈与税の課税価格
■改正の概要
相続時精算課税の適用を受けた贈与に係るその年分の贈与税については、暦年課税(暦年贈与)の基礎控除とは別に、毎年、贈与額から基礎控除110万円を控除できることになります。
計算式
{(贈与税の課税価格-基礎控除)-特別控除額}×20%
※相続税の課税価格に加算する財産の価額:(贈与税の課税価格-基礎控除)
👉ポイント
この基礎控除は、複数の特定贈与者(財産をあげる人)から贈与を受けた場合にはそれぞれの贈与額で按分することになります。
【解説】
例① 祖父、祖母から、暦年贈与によりそれぞれ110万円、合計220万円の贈与受けた場合。
※220万円-110万円(基礎控除)=110万円
110万円に贈与税がかかります。
例② 父から、110万円の暦年贈与、母から相続時精算課税による贈与110万円を受けた場合。
※ 父からの贈与分:110万円-110万円(暦年分の基礎控除)=0
※ 母からの贈与分:110万円-110万円(相続時精算課税の基礎控除)=0
よって、申告不要となります。
母からの贈与について相続時精算課税の初年度の場合、「相続時精算課税選択届出書」を
申告期限までに納税地の所轄税務署へ提出する必要があります。(2年目以降不要)
例③ 父と母からそれぞれ相続時精算課税により110万円の贈与を受けた場合。
(それぞれ初年度の場合)
※ ㋑ 父からの贈与分:110万円-55万円(基礎控除)=55万円
㋺ 55万円-55万円(特別控除額)=0 → 税額は生じませんが申告が必要
〈父からの贈与分に対する基礎控除〉
110万円(基礎控除)×110万円(父〉課税価格)/220万円(父と母の課税価格の合計)
=55万円
※ ㋩ 母からの贈与分:110万円-55万円(基礎控除)=55万円
㊁ 55万円-55万円(特別控除額)=0 → 税額は生じませんが申告が必要
〈母からの贈与分に対する基礎控除〉
110万円(基礎控除)×110万円(母の課税価格)/220万円(父と母の課税価格の合計)
=55万円
※ 父と母からのそれぞれの贈与について初年度ですので「相続時精算課税選択届出書」を
申告期限までに納税地の所轄税務署へ提出する必要があります。(2年目以降不要)
■結論
相続時精算課税制度の基礎控除を理解しないまま選択してしまうと、こんはずではなった
基礎控除110万円となってしまいます。
つまり、申告不要だと思ったのに必要になった。相続税の課税価格に加算される金額が増えてしまった。
申告不要だと思ったのに後日申告が必要となった場合・・・・申告期限後に申告することとなった場合、特別控除額を控除することができないため20%の税率で贈与税が発生します。
相続時精算課税制度を一度選択してしまうと撤回できないため、二度と暦年課税による贈与には戻ってこれらません。要注意です。
2025年2月25日
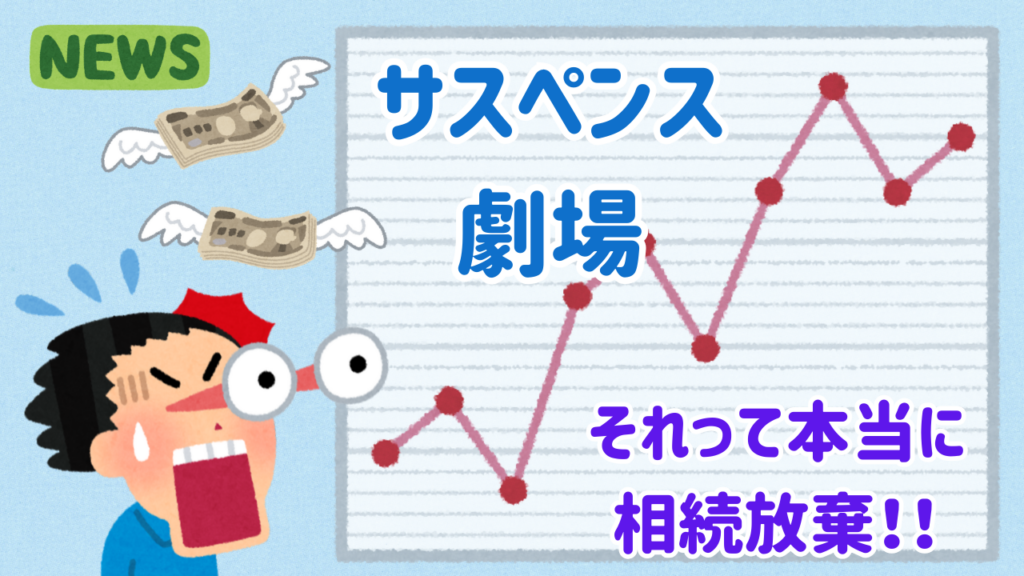
相続放棄の実際の手続きとその流れ
自称サスペンスの帝王は見た~!!
サスペンスの場面ではこんなこと言っていなかった。
サスペンスのワンシーンで出てくる、八百屋の前で会議をしている奥様の会話です。
私は相続放棄したのよ・・・・・。
はんこだけ押してあげたのよ・・・・。
これは、財産をもらわなかっただけで、相続放棄をしたわけではありません。
実際の相続放棄の手続きは次の流れで行います。
相続放棄をすると、遺産分割協議書に押印することはありません。
◆相続における3つの選択
相続が発生すると相続人となる者は、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)、もしくは限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)、または相続放棄(遺産の相続を放棄しプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)のいずれかを選ぶことになります。
相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、借金がなくとも相続にかかわりたくない、財産分与ゼロでハンコを押すのはしゃくだなど、他の理由であっても自分の意思で選べます。
◆相続放棄の手順
(1)家庭裁判所へ相続放棄を申述する
相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならないと定められています。申述書に申述内容を記入し、被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して家庭裁判所に書類を送ります。
(2)家庭裁判所から「照会書」が届く
申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、①誰かに強要されたり、②他人が勝手に手続きしたり、③相続放棄の意味がわからず手続きしていないかなど、その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。
書類をよく読んで、真意である旨を「回答書」に自筆で記載し期限内に返送します。
(3)「相続放棄申述受理通知書」で完了
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)が届いて手続き完了となります。
なお、他の相続人が相続手続きをする際に「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、事前に受理証明書の交付申請を行えば受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。
◆相続放棄のデメリット
相続放棄が完了すると後から撤回できないため、相続放棄完了後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできません。また、他にも個々の事情で発生するデメリットもあり得ます。放棄に際しては、司法書士などの専門家に相談しながら手続きすることをお勧めします。
2025年1月20日

桐生税理士事務所は、秦野市を拠点に「日本一相談しやすい事務所」を目指しています。25年以上の経験を活かし、相続税や法人税、所得税など幅広い税務のサポートを提供。年間4,500件以上の相続税申告実績を持ち、銀行や証券会社での相談経験も豊富です。初回相談は無料で、事前予約により夜間や休日の対応も可能。秦野駅から徒歩10分とアクセスも便利です。神奈川県で税務相談をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
税務会計 / ワンポイント

最低賃金全国平均は・・・・?
全国加重平均66円上げ過去最大
神奈川県の最低賃金は時給1,225円。全国平均は時給1,121円。
中央最低賃金審議会で賃金引き上げ額が全国加重平均は24年度実績から66円引き上げ時給1,121円で決まりました。現在の1,055円から上昇率6.2%と金額、率とも過去最大規模のアップです。引き上げは23年連続で、目安以上の引き上げがされて全ての都道府県で1,000円を超えています。
発効日は2025年10月ですが、今年は半分以上の府県は11月以降になります。
中小企業の経営には生産性の底上げが急務
中小企業者に対し日本商工会議所が2025年1月~2月に行った調査では、最賃上げ対策としては「設備投資等人件費以外のコスト削減」(39.6%)「残業時間・シフトの削減」(31.3%)となっていました。引き上げに見合う経営体力が伴わなければ、高い賃金を提示されても重荷となり人材採用、雇用維持ができず地域経済がしぼむリスクもあります。
労働政策研究・研修機構が実施した調査では最も低いパート賃金が「最低賃金の10%以上上回る」と答えた企業は26.7%しかありません。社会保険料がかかり始める「106万円の壁」に達する人も増えていくでしょう。
最低賃金の近くで働くパートやアルバイトは多く、基準となる金額の引き上げで社会保険料がかかり始める人が増えてきます。社会保険料の支払いを回避して働き控えをする人も一定数います。最低賃金の引き上げが人手不足に拍車をかけることにもなりかねません。
準備期間は限られている
例えば、最低賃金で1日8時間、21日働くパートの場合、1,055円×8H×21日=177,240円だった月給が1,121円×8H×21日=188,328円となり、差額は月11,088円、年間で約13万円超の増加です。
ある飲食店の対応策例では、
・ピーク時間のみ勤務の「短時間勤務に」切り替え
・夕方以降の清掃を外注に切り替え
・接客業務のセルフ化、タブレットの活用
・売上げが少ないメニューの廃止 等
時給制社員の最賃改定後の賃金シミュレーション、人件費総額の影響試算、不採算業務の作業の洗い出しなどで作業の見直し等をしてみましょう。
掲載日:2025年10月25日
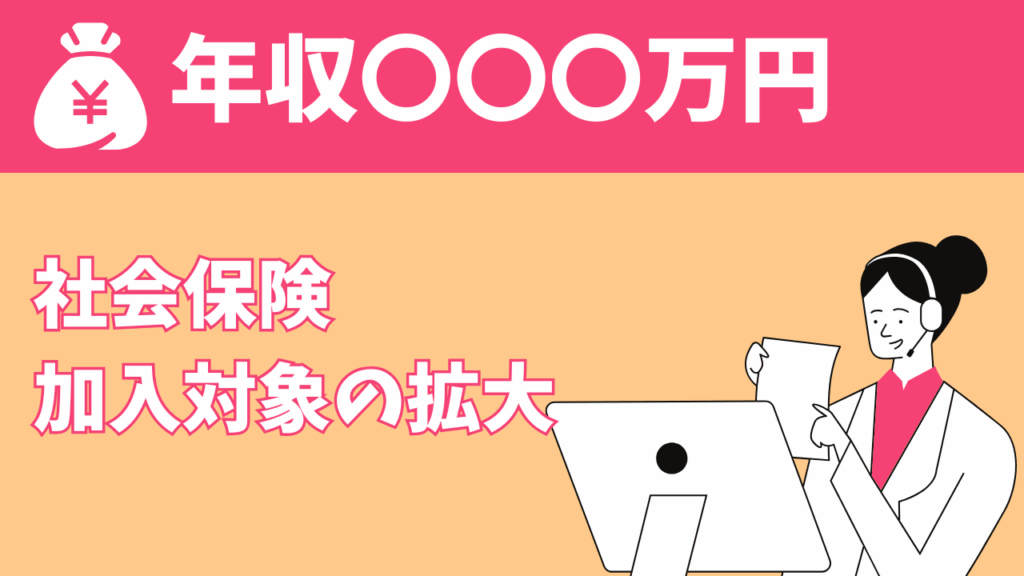
社会保険加入対象の拡大・・・?
年金制度改正法可決・成立
年金制度改正案が6月13日に国会で通ったことで厚生年金保険・健康保険の適
用拡大が決定しました。この改正によりパート・アルバイトなどの社会保険加入
対象の範囲がさらに拡大されます。今後の具体的な内容を見てみます。
企業規模要件の縮小・撤廃
現在、社会保険加入の企業規模要件は、従業員数51人以上の企業に勤務してい
る週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者です。2027年(令和9年)10月
以降は企業規模を段階的に縮小し、2035年(令和17年)10月には完全撤廃になり
ます。
賃金要件の撤廃
「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円(年収106万円)の
要件も撤廃となります。撤廃の時期は、改正法の公布から3年以内の政令で定め
る日とされていますが、最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと年額
換算で約106万円となります。よって全国の最低賃金が1,016円以上となることを
見極めて判断されます。
個人事務所の適用対象拡大
現在5人以上の従業員を使用している法定17業種(弁護士・税理士・社会保険
労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業等)の個人事業所が社会保険加入対象
になっています。今回の改正では、法定17業種に限らず常時5人以上の従業員を
使用する全業種の事業所が適用対象となります。ただし施行時点の2029年(令和
11年)10月に既にある事業所は当分の間対象外です。
支援策は?
この改正で加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、3年間、特例
的、時限的に保険料負担を軽減する措置が実施されます。対象となるのは従業員
数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険
の加入対象となる、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者です。
また、正社員化や労働時間の延長や賃金アップに取り組むことで支給される助
成金もあります。
掲載日:2025年10月21日
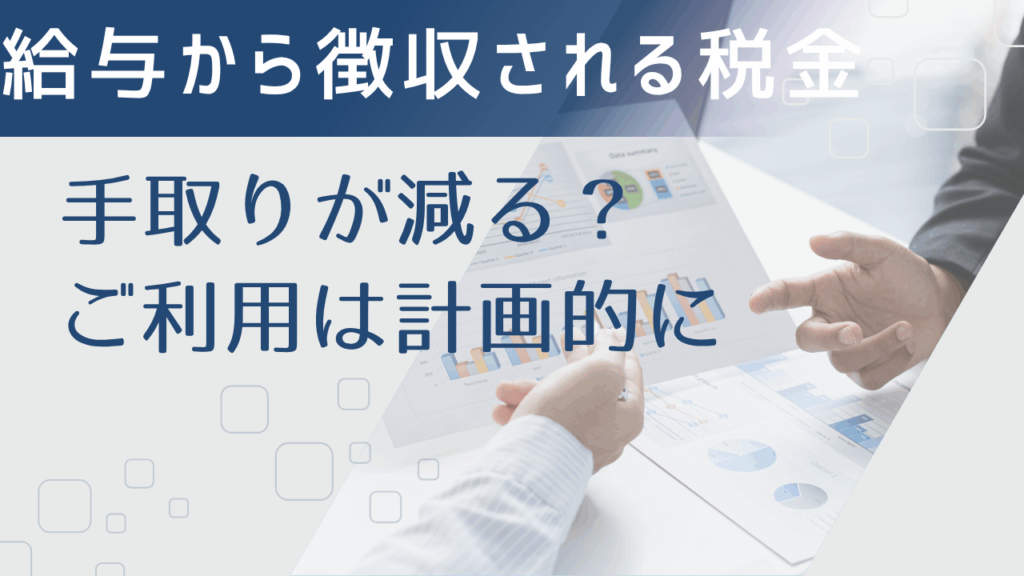
給与から徴収される税金・・・・2年目からの手取りが減る?
2年目から手取りが減る?
新卒で入社した方は、この春が初任給という方も多いでしょう。日経新聞がま
とめた2026年度採用計画調査によると、物価上昇を背景にしてか25年度の初任給
を30万円以上とする企業が24年度から倍以上に増えたそうです。
給与から徴収される税金は「所得税」と「住民税」ですが、住民税については
昨年1~12月の所得や控除で今年6月からの住民税が計算されるため、新入社員の
1年目の給与からは学生時代のアルバイト量がよほど多くない限り、住民税が徴
収されません。2年目6月の給与から、1年目の所得や控除に応じて住民税が天引
きされるようになるため、手取りが減るという現象が発生します。初任給から2
年目の給与が10%以上増えれば話は別ですが、昇給率がそこまで高い会社は珍し
いでしょう。
なお、転職の場合は前の会社で異動届出書を作成、新しい会社に提出していれ
ば住民税の特別徴収が継続されます。
所得税の源泉徴収義務
給与所得に対しては所得税・住民税共に「事業主が徴収しなければならない」
とされていますが、除外される例外もあります。所得税の徴収義務の例外として
は、扶養控除等申告書を提出している場合、給与収入が月額88,000円未満であれ
ば徴収しなくてよいことになっています。
住民税の徴収義務
住民税の天引きについては「特別徴収」と少し呼び名が変わります。また、徴
収義務は所得税同様ありますが、以下の場合は天引きではなく納税者が納める「
普通徴収」でもよいということになっています。
・事業所の総従業員数が2人以下
・別の事業所で特別徴収
・給与が少なく税額が引けない
・給与支払いが不定期(毎月でない)
・事業専従者(個人事業主のみ対象)
・退職者又は退職予定者(5月末まで)
ご利用は計画的に?
一般的な会社勤めであれば、所得税と住民税は天引きされるのが普通ですが、
2年目新たに発生する住民税の徴収は所得税と比べると税率が10%固定の分、稼
ぎがまだ少ない新人にはそれなりにつらい手取りの減少となります。職場の先輩
方は2年目から住民税が徴収される旨を早めにアドバイスしてあげるとよいかも
しれません。
掲載日:2025年7月19日
税のことだってセカンドオピニオン

「セカンドオピニオン」、皆様も一度は聞かれたことのあるのでは?
直訳すると「第2の意見」という意味で、現在は主に医療の場面で、主治医とは異なる医師に、自身の病状や治療方針について相談し、意見をもらうことを示しています。
少し前、知人がちょっとした手術を受けました。診断もなかなかつかず、手術の方法も主治医と紹介先の医師とで違ったそうですが、様々な視点から説明を受けることで、自分の選んだ方針を、より納得して受け入れることが出来たとのこと。
本来は長年診てもらっている先生が、自分のことを一番分かってくれているはず。でも、だからこそ、「ちょっと聞きづらい…。」ということも当然あるのでは?
医療については当たり前になってきたセカンドオピニオンの考え方、皆様の大切な資産についても当てはまるのではないでしょうか?
「とりあえず利益は出ているけど、会社の資金繰り、これでいいのかな?」「銀行から贈与について提案があったけど、それって本当に良い方法なのかな?」
お金が動けば、そこに何らかの税が発生する可能性は大いにあります。つまり税の専門家は「お金の専門家」でもあるのです。現状について、ふと疑問に思われた時は是非、税の専門家である税理士にご相談下さい!
〇 顧問税理士との契約はそのままに、
〇 顧問とは別の相談相手として、
例えば、
・相談事項について、複数の見解を得て客観的に判断したい
・法人顧問は、今の税理士先生で、個人(社長)のことは、資産税が得いな税理士へ
依頼したい
などなど・・・
お気軽にご連絡ください。
桐生税理士事務所がサポートします。
掲載日:2025年5月13日
中小企業のリース会計と法人税
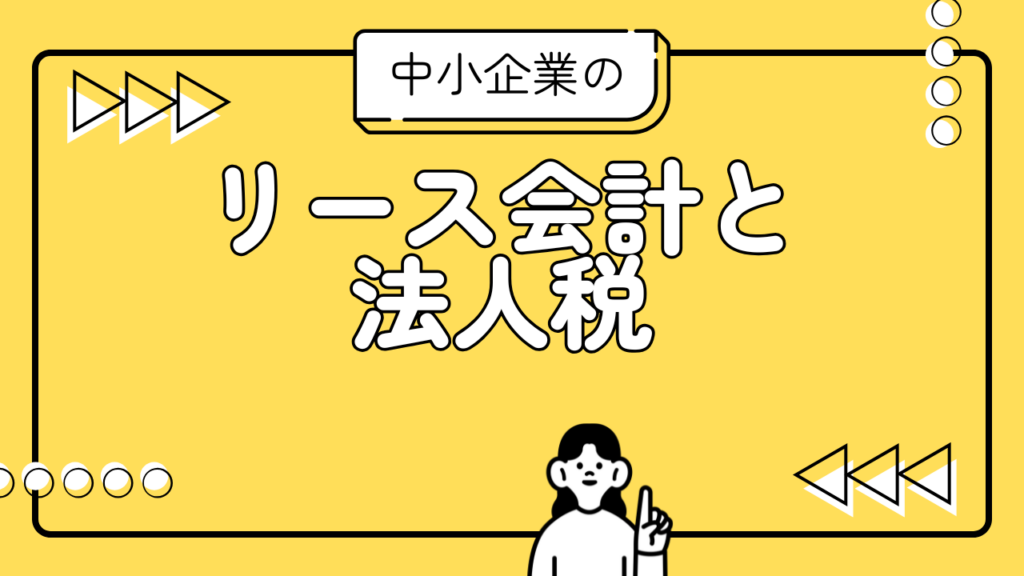
2024年(令和6年)9月に新リース会計基準が公表されました。
2027年(令和9年)4月1日以後開始する事業年度より適用されます。
なお、新リース会計基準は、いわえる上場企業などの金融商品取引法の適用を受ける会社等(公認会計士または、監査法人の監査を受ける会社)が対象で、中小企業は「中小企業の会計に関する指針」に従って対応する必要があります。
細かい論点はありますが、簡単に整理してみましたのでご活用ください。
◆リースとは所有せずに使用する契約
リースは他人から特定の資産を一定期間、リース料を支払って使用する契約を
いいます。契約期間にわたり支払を分散させることができます。
ファイナンス・リースは中途解約できない代わりにリース資産を使用して経済
的利益を受けることができ、リース期間終了までリース料を支払うもの、オペレ
ーティング・リースはファイナンス・リース以外のリースをいいます。
◆上場会社等のリース会計は売買処理に統一
上場会社等のリース取引に適用される会計基準は、ファイナンス・リースはリ
ース資産を売買があったものとして資産として計上します(売買処理)。オペレ
ーティング・リースはこれまで賃貸借として扱っていましたが、新リース会計基
準の適用により資産計上(売買処理)となりました。
◆中小企業のリース会計は賃貸借処理のまま
中小企業のリース会計は、中小企業向けの会計ルール(中小企業会計指針、中
小企業会計要領)によることができ、ファイナンス・リース、オペレーティング
・リースともに賃貸借処理が適用できます。新リース会計基準は強制適用されず
、従来どおり賃貸借処理が継続できます。
◆上場会社等の法人税の扱い
上場会社等がファイナンス・リースを受けた場合の法人税の扱いは、少額リー
ス、短期リースを除き、売買処理が適用されます。このうち所有権移転外リース
については資産計上額をリース期間にわたり月数按分で減価償却します。一方、
オペレーティング・リースを受けた場合は賃貸借処理が適用されます。会計では
元本部分と利息部分を分けて処理するので法人税の処理と一致しなくなり、申告
調整が必要となります。
◆中小企業の法人税は賃貸借処理のまま
中小企業のファイナンス・リースに係る法人税の扱いは賃貸借処理が適用され
、賃借料として損金経理した場合はリース資産の償却費とみなして損金に算入さ
れます。(売買処理も可能)
また、オペレーティング・リースに係る法人税は、新リース会計基準の導入後
も賃貸借処理が継続されます。令和7年度税制改正大綱では、オペレーティング
・リースで法人が支払うリース料について「債務の確定した部分の金額は、その
確定した日の属する事業年度に損金算入する」と記載されており、この文言から
従来の賃貸借処理のままとなると解されます。
掲載日:2025年5月2日
事業の成績表
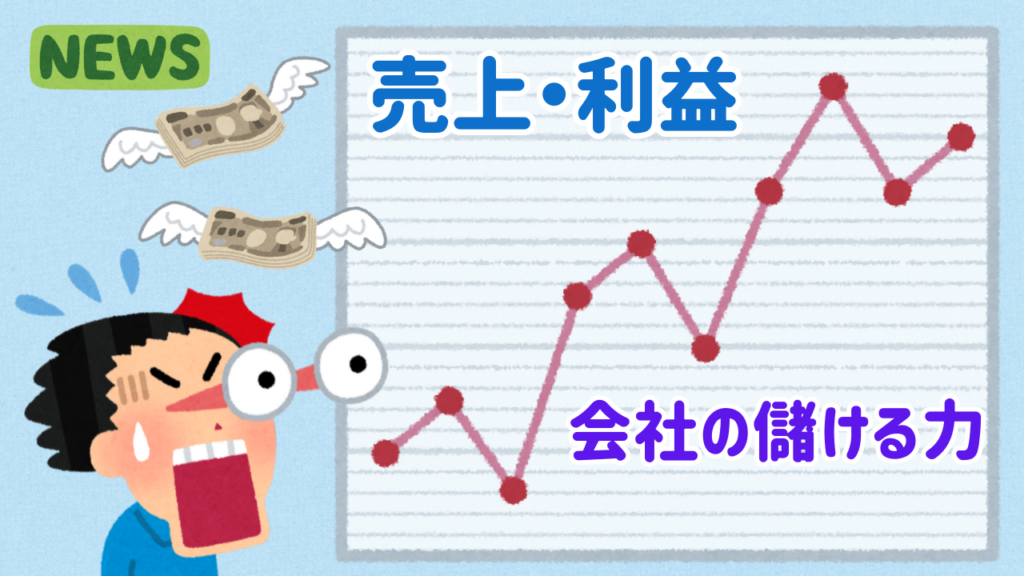
事業の成績表の分析で利益を多く残す工夫につなげましょう。
会社が獲得した利益のことを一般的に「儲け」といいます。そして会社が儲けを生み出す一連の活動を経営活動といいます。そのため、会社の経営状態を把握しようとすると、【会社の儲ける力】を見ることになります。
◆決算書=事業の成績表を分析していますか?
決算書は一年間の事業の成績表です。個人事業の場合は暦年決算なので、1~2月頃には前年の成績表ができているでしょう。決算書をどう見ていますか。単に前年より増えた減っただけで終わっていませんか。
もう少しだけ比較対象を拡げ、同規模の同業他社と比べ、自社の強みと弱みをしっかりと認識するところまで、決算成績表を活用してみませんか。
◆自業種での適正な原価率・人件費率等は?
飲食店経営の場合を例にします。「食材費」と「人件費」の「売上高」に占める割合を「FL比率:F=Food、L=Labor」といい、一般的にFL比率の適正値は60%以下といわれています。FL以外の経費(店舗家賃、水道光熱費、機器のリース料など)が30%超えることが多いため、FL比率が70%を超えてくると、利益がほとんど残らなくなり、立ち行かなくなります。そのため、飲食店経営においては、FL比率を常に把握し、改善をしてゆくことが、経営を安定させることにつながります。
◆利益増は売上増か経費の削減
利益増には、売上を増やすか、経費を減らすか、その両方かということになります。
売上=客数×客単価です。あなたのお店で客数・単価を増やすには、どんな方法がありそうですか。座席数を増やせないか、回転率を上げられないか、客単価を増やすには何か策がないか等々、検討し実行すべきアイデアがいくつか出てくるでしょう。
経費の削減については、食材費の質を落とすと客離れにつながるので、ムダがないかの検証が必要です。同じ食材でも購入方法いかんで仕入額が高くなっていませんか。業務卸店で仕入れるのではなく、面倒だからといって近所のお店で一般消費者と同じ値段で購入などしていませんか。食材ロスの減少はできそうですか。また、常連客へのサービスとして盛りを大きくして原価増となっていませんか。こうしたものがあれば即見直しが必要です。
人材配置も過剰に心配して厚く集めすぎていませんか。効率的な動き方の業務マニュアルの作成などでムダな人件費の発生の抑制も目指しましょう。
数字を比較・分析して、いろいろな工夫をし、多くの利益が残るような成果につなげてください。
掲載日:2025年3月23日
資本的支出と修繕費の区分
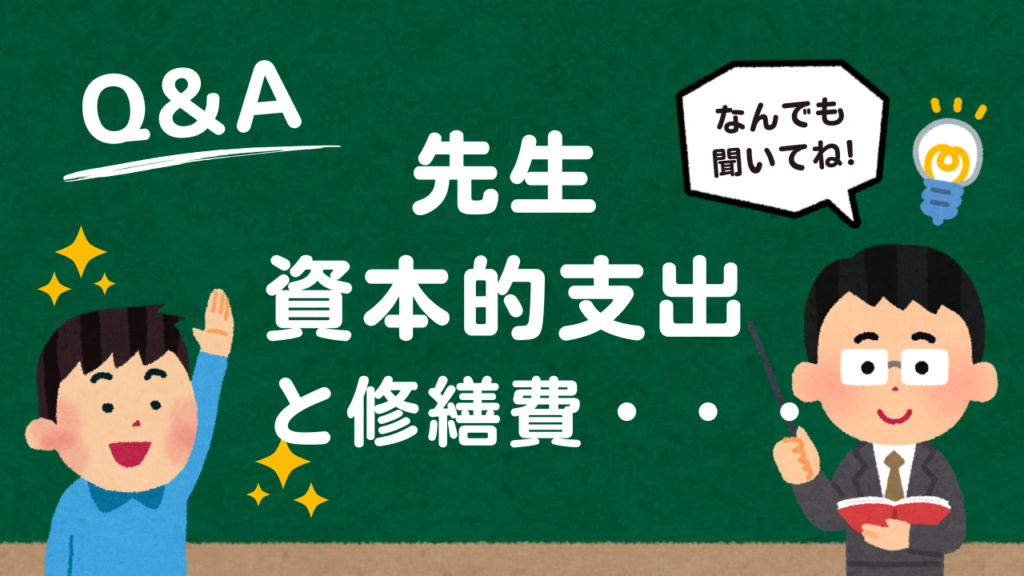
どこまでが修繕費?いや全部修繕費にきまってる~。
税務調査でもトラブルになりやすい修繕費の基本的な考え方をご紹介します。
適正な税務申告には、固定資産の修繕や改良に要する費用の区分が重要です。実務では、「資本的支出」と「修繕費」の明確な区分が難しいケースが多く、特に機能回復を目的としつつ高機能化や耐久性向上が伴う場合は、判断が困難となります。
◆資本的支出と修繕費の定義と区分基準
「資本的支出」は固定資産の機能のアップグレードや耐久性を増加させる支出で、取得価額に加算し減価償却を通じて費用化されます。
「修繕費」は固定資産の維持管理や原状回復のための費用で、発生した事業年度の損金算入が可能です。
※上記は一般的に資本的支出の例示、修繕費の例示とも言われています。
第8節 資本的支出と修繕費|国税庁
◆判断が難しい事例:蛍光灯のLED化
LED化による節電効果や耐久性向上から、一見「資本的支出」と考えられるかもしれません。しかし、実務では「照明設備」の消耗品の交換とみなし、全体の価値向上とはせず、「修繕費」として処理することが適切です。
◆修繕費として認められる場合
以下の条件を満たす支出は、修繕費として処理することが認められています。
①定期的な修理: おおむね3年以内の周期で行われる修理や改良
②少額の支出: 一回の修理や改良の金額が20万円未満の場合
③修繕費の例示に該当するもの
④上記に当てはまらない、または、判断が困難な場合: 資本的支出か修繕費か明確でない場合で、その金額が60万円未満、または資産の前年度末取得価額の約10%以下の場合
◆判例にみる資本的支出と修繕費の判断
賃貸マンションの台所・浴室設備全面取替工事が争点となった国税不服審判所の平成26年4月21日の裁決(平成21、22年分の所得税)では、納税者は居住機能回復の修繕と主張するも、既存設備撤去と新設備設置は修繕を超え、資産価値を高め耐久性を増す資本的支出と判断されました。
この裁決は、工事目的が機能回復でも、内容が実質的に資産価値向上なら資本的支出となることを示しています。
掲載日:2025年2月10日
新リース会計基準について
◆リース会計基準改正の公表
2024年9月13日、企業会計基準委員会が「リースに関する会計基準」の改正を公表しました。新基準は国際基準との整合性を図り、リース取引を財務諸表により正確に反映するためのものです。
◆新たなルールのポイント
今回の改正では、借手のすべてのリースを資産と負債に計上する「単一の会計処理モデル」を採用します。オペレーティング・リースを含むリース契約を「使用権資産」として資産計上し、リース料の支払い義務を「リース負債」として負債に計上することが求められます。これにより、リースの実態がより透明性を持って財務諸表に示されることになります。
◆適用日と早期適用について
新基準の適用開始日は2027年4月1日以降に始まる連結会計年度および事業年度からとなります。ただし、2025年4月1日以降に始まる年度からの早期適用も認められています。
◆すべてのリースを財務諸表に計上
新基準では、従来貸借対照表に計上されていなかったオペレーティング・リースも含め、すべてのリースが計上対象になります。これにより、リース取引の内容が財務諸表により正確に反映され、企業の資産・負債状況が明確に示されます。経営判断の透明性が高まり、財務報告の信頼性が向上する点が新たなルールの特徴です。
◆財務指標への影響に注意
リース負債の計上により、自己資本比率や負債比率などの財務指標に変動が生じる可能性があります。特に中小企業では、信用評価や金融機関との取引条件に影響を及ぼすことが予想されます。そのため、早めにリース契約や資金計画を見直し、新基準適用の影響を把握することが必要です。 ◆今後の対応策
適用日までに十分な準備期間はありますが、早めの対応が求められます。まずは現在のリース契約を精査し、新基準に基づく会計処理の対象となるリースを特定しましょう。また、専門家と連携し、財務諸表への影響を最小限に抑える戦略を立てることも有効です。新基準への適切な対応は、企業の財務健全性を維持するために欠かせないものです。
掲載日:2025年1月6日
申告書に収受印を押してくれない
◆令和7年1月以後は
国税庁は今年1月4日、令和7年1月以後は申告書等(国税に関する申告、申請、請求、届出等税務署に提出される全ての文書)の控えへの収受日付印(税務署名や年月日等)の押捺の実務慣習を廃止する、と公表しました。
申告書等の持参又は郵送に対する措置です。e-Taxによる申告では、“受信通知”がメッセージボックスに格納されます。税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の推進が目的です。
また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。
◆申告書等提出事実を証明する方法
それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを証明すればよいのでしょうか。
①Q&Aをネット公開し、令和7年1月以後の当分の間の対応として、窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、希望者に配付する、この配布文書は提出事実の証明機能を持つ、と回答しています。
②所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、申告済みの申告書等を閲覧することができます。そこには収受印が押されています。閲覧に手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、コヒーの提供は受けられません。ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで写真撮影が可能となります。
③納税証明書の交付請求を行い、納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済み申告書の内容を間接的に証明します。
④個人だけのケースとしては、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)などがあります。
◆銀行等は対応を変えないと
これまで、銀行への融資申請や、住宅・自動車等のローン審査、奨学金の申請、自治体への補助金・助成金の申請、小規模企業共済、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)等々で、確定申告書の提出控えを求められていました。今後は、どうなるのでしょうか。
掲載日:2024年12月20日

桐生税理士事務所は、秦野市を拠点に「日本一相談しやすい事務所」を目指しています。25年以上の経験を活かし、相続税や法人税、所得税など幅広い税務のサポートを提供。年間4,500件以上の相続税申告実績を持ち、銀行や証券会社での相談経験も豊富です。初回相談は無料で、事前予約により夜間や休日の対応も可能。秦野駅から徒歩10分とアクセスも便利です。神奈川県で税務相談をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
所得税・確定申告 / ワンポイント
絶対に忘れてはいけない・・・定額減税!!
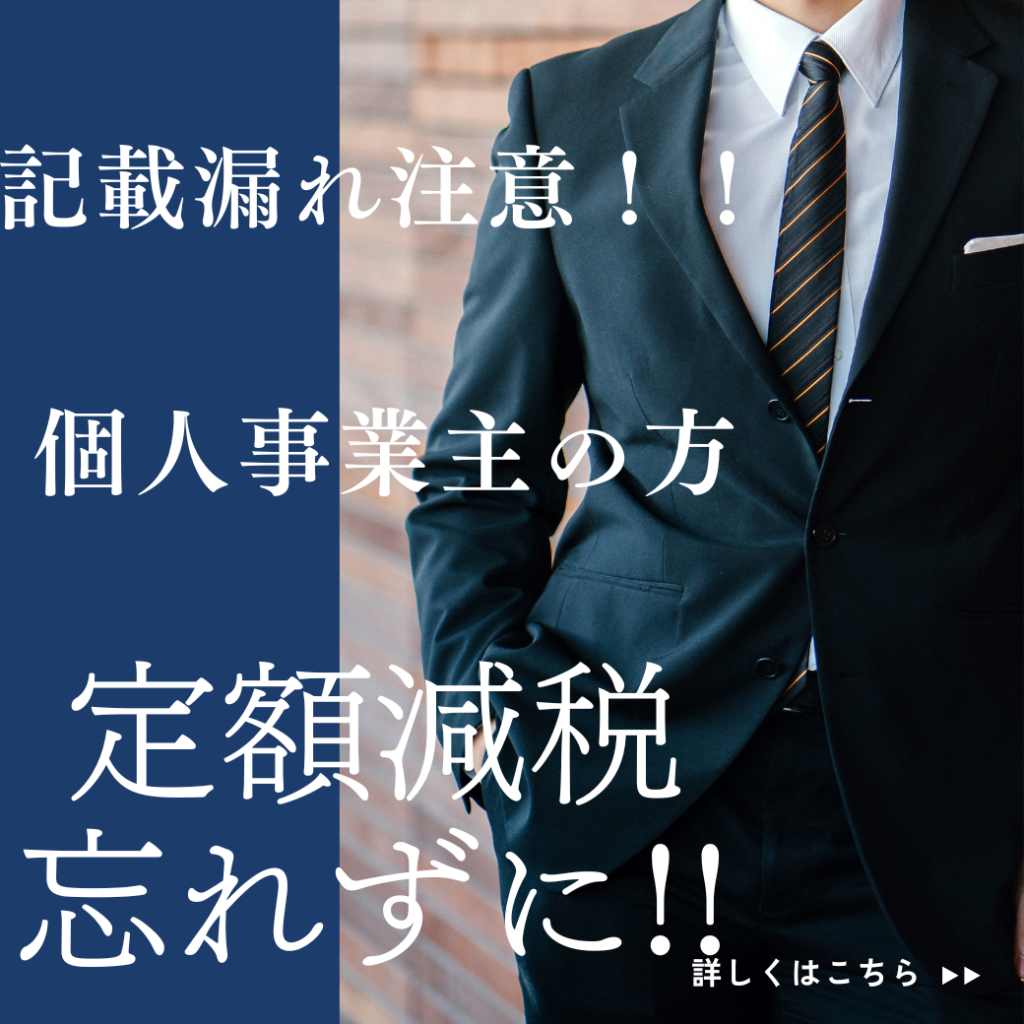
記載漏れには注意!! そして確定申告はお早めに~
個人事業主の方!!定額減税忘れずに。
そして、確定申告は早めに終わりにしましょう!!
令和6年分の確定申告期間は、
令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までです。
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
具体的には、一定の要件を満たす納税者本人、配偶者や扶養親族1人につき、所得税から3万円、住民税から1万円が控除されます。
個人事業主の方は確定申告で控除を受けます。
記載漏れがないようにしましょう。
〈定額減税対象者〉
・納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。
・同一生計の配偶者、同一生計の扶養親族で合計所得金額が48万円以下(給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下である方)
事業専従者の方は除かれますが、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は、扶養控除の対象には該当しませんが、定額減税を受けることができます。
年金と税制
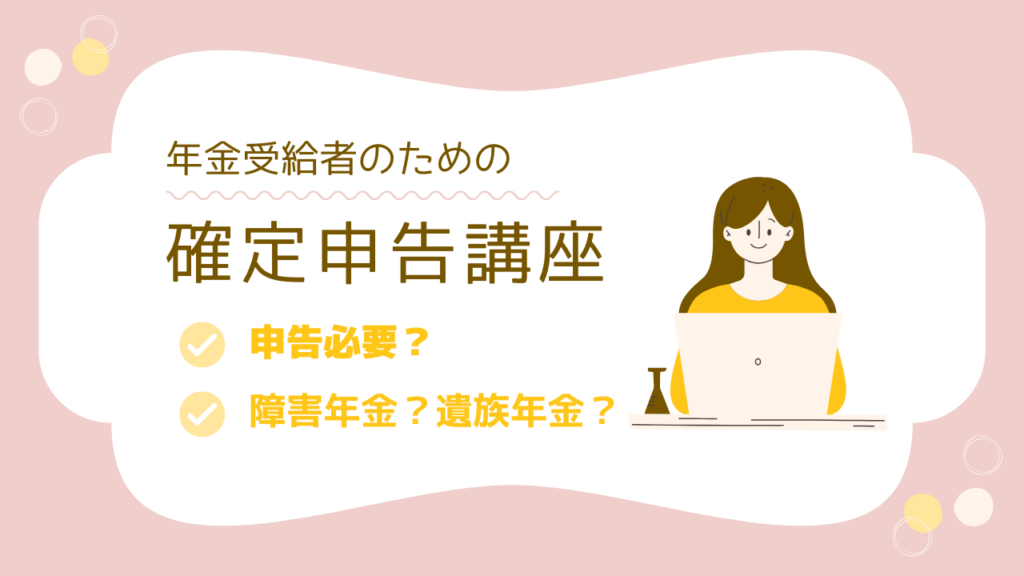
公的年金受給者の確定申告についてご案内します。
公的年金等とは、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金のほかに、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給される年金等です。(一部省略)
なお、生命保険契約等に基づいて支給される年金は該当しません。
◆公的年金受給者で確定申告が不要な場合
公的年金受給者で確定申告が不要なのは、以下の人です。
・公的年金等の額が400万円以下の人・公的年金等以外の所得が20万円以下の人
・公的年金等の源泉徴収票の源泉徴収税額欄が0円の人
※年金受給者の負担軽減を目的に確定申告不要制度が設けられています。
◆公的年金受給者で確定申告が必要な場合
公的年金受給者で確定申告が必要なのは、以下の人です。
・公的年金等の収入が合計400万円を超える人
・公的年金等以外にも収入がある人
・所得控除を受けたい人(生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除など)
◆老齢年金は課税、障害・遺族年金は非課税
公的年金給付は受給権者の生活の安定のため、支給を受けた金額が租税等の課税対象とならぬよう課税対象から外されています。ただし例外的に老齢年金は課税対象とされています。これは、老齢への備えとして保険料納付実績に比例した給付であり、一種の貯蓄的な性格や給与の後払い的な性格があること、保険加入中に被保険者として納付した保険料は社会保険料控除として拠出段階ですでに非課税であること等を勘案したものとされています。
障害年金と遺族年金はあらかじめ発生を予期できないリスクに対応して給付を行うもので非課税とされています。
◆公的年金は公的年金控除の対象
公的年金等の収入は雑所得に区分され、公的年金等控除額を差し引いて、所得金額を計算します。公的年金控除の額は定額控除40万円と定率控除(50万円を差し引いた後の年金の収入に応じて、25%、15%、5%と段階的に減少)を合計し、合計額と最低保障額(国民年金基金、65歳以上は110万円、65歳未満は60万円)の大きい方の額になります。
公的年金控除は基礎年金、厚生年金、厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型・個人型iDeCo)等が対象です。
◆老齢年金でも一定額以下は非課税
単身者で公的年金控除の最低保障額110万円と基礎控除48万円に支払った医療保険料、介護保険料等の社会保険料控除を加えた額が所得年金収入158万円に社会保険料の額を加えた額以下の場合は、課税所得がないので所得税は非課税になります。
住民税を見ると公的年金等控除最低保障額110万円を差し引いた額が均等割り非課税基準以下の場合は非課税です。非課税基準は自治体により異なりますが、東京23区や指定都市の基準は同じです。
年金に所得税がかかる場合は、日本年金機構が年金支給額から所得税を源泉徴収して国に納付します。公的年金等以外の所得が20万円を超える場合や公的年金等の収入が400万円を超える場合は確定申告が必要です。

桐生税理士事務所は、秦野市を拠点に「日本一相談しやすい事務所」を目指しています。25年以上の経験を活かし、相続税や法人税、所得税など幅広い税務のサポートを提供。年間4,500件以上の相続税申告実績を持ち、銀行や証券会社での相談経験も豊富です。初回相談は無料で、事前予約により夜間や休日の対応も可能。秦野駅から徒歩10分とアクセスも便利です。神奈川県で税務相談をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。