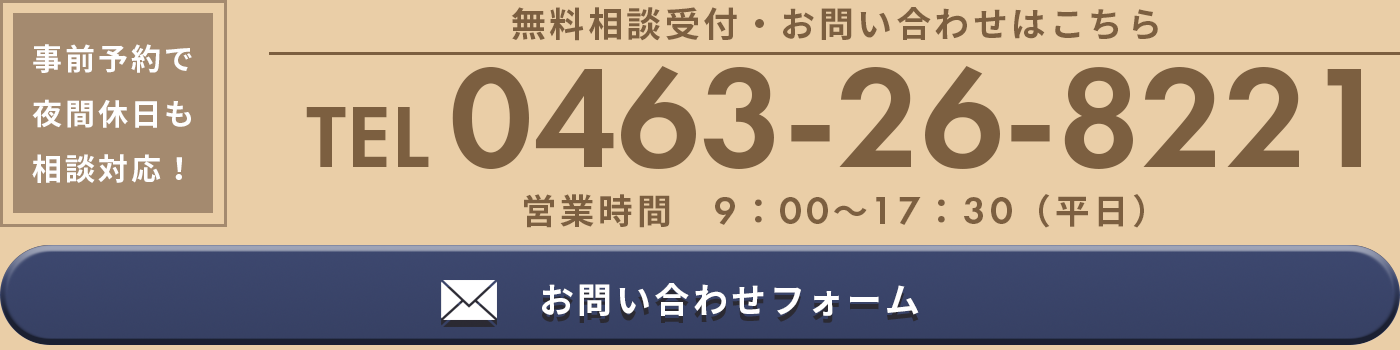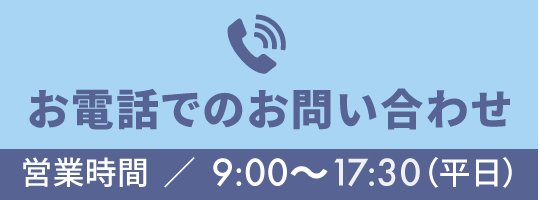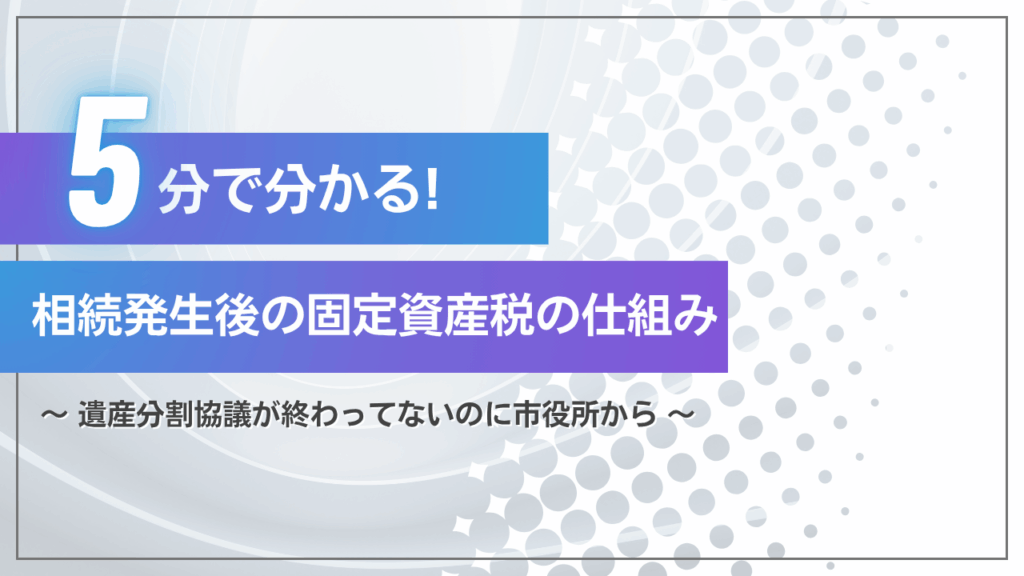
このページの目次
遺産分割協議が終わってないのに固定資産税の納付書が・・・・誰が払う?
土地・家屋の現所有者申告
遺産分割協議が終わらないうちに役所から固定資産税の案内が届くことがあります。これは土地や家屋を相続して新たに固定資産税を納付する人を役所に届け出るもので土地・家屋の現所有者申告と呼ばれます。
固定資産税の仕組み
固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に課される地方税です。市町村(東京23区は東京都、以下同)は不動産登記簿等に記載された土地・家屋の所有者に毎年5月頃、納税通知書を送付します。
固定資産税の評価額は地方税法に定める固定資産評価基準により、市町村が決定します。3年に一度、評価替えが行われ、直近では令和6年度に改定されています。
相続で納税義務も承継される
相続人は被相続人の土地・家屋取得に伴い、固定資産税の納付義務も承継します。市町村が現所有者申告の手続を求めるとき、現所有者は遺言や遺産分割協議で土地・建物を取得した者だけでなく、遺産分割協議前の法定相続人も該当します。
民法では相続があると、法律で定められた順番に相続人が決まり、法定相続分により財産・債務を承継します。したがって遺産分割前は相続人全員が現所有者となって固定資産税の納付義務を負うことになります。そして市町村は相続人の中から代表者を決めて、その者に納付してもらうこととしています。
現所有者申告書の提出期限は相続開始後3月とされており、具体的には市町村ごとの条例で決められています。届出書の様式も市町村ごとに定められており、ホームページに記載例が掲載されています。
現所有者申告書の添付書類には、相続人全員の戸籍謄本や住民票の提出を求める市町村や本人確認票(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示だけですむ市町村もあります。
相続人代表者が固定資産税を一度納付する
遺産分割協議前の固定資産税の納税義務は相続人全員にありますが、実務上は相続人代表者が一度納付し、後に相続人の間で各自の持分で精算します。土地・家屋の取得者の相続登記が行われると、以降は新しい所有者に納税通知書が送付され、共有の場合は引き続き代表者に送付されます。
なお、相続した不動産を売却したり抵当権を設定したりするためには相続登記(所有権移転登記)が必要となりますので忘れないようにしましょう。
2025年7月9日
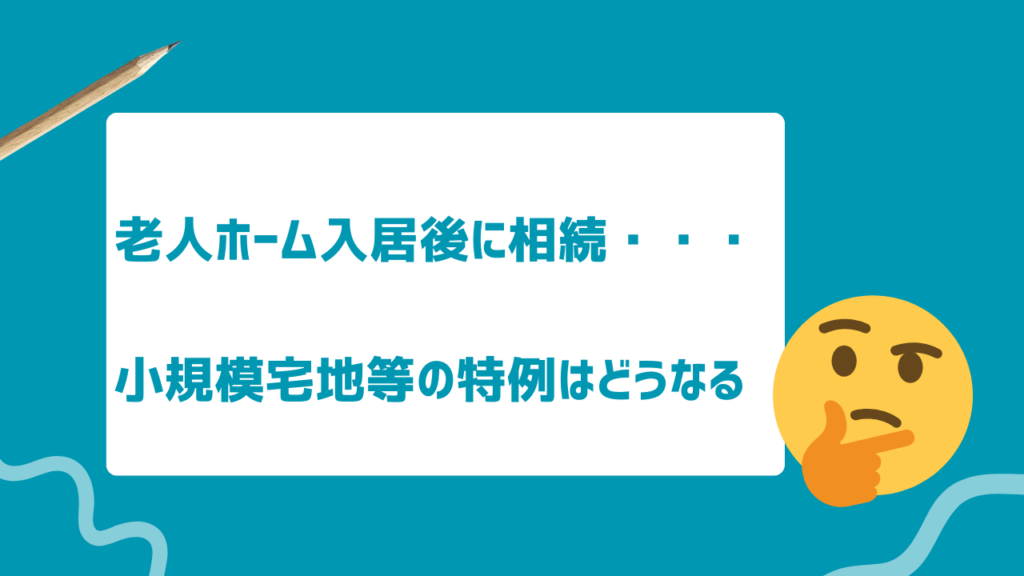
知らないと損する・・・?
小規模宅地等の特例 ~老人ホーム入居後に相続~
老人ホーム入居後に相続が発生した場合の小規模宅地等特例の適用可否
高齢化社会になり、親が老人ホームに入所するケースが増えており、寿命の内、健康寿命を超える要介護期間が、男性9~10年、女性12~13年程度とされているので、最近の傾向としては、介護が必要となってからの入所よりも、元気なうちから入所を決める傾向になっています。
それでは、老人ホームへ入居した後に相続が発生した場合の小規模宅地等の取扱いについて検討したいと思います。
居住用小規模宅地等の特例
平成25年度の税制改正において、老人ホームへの入所まで居住していた自宅の敷地に係る相続税の小規模宅地等の特例の適用について、一定の要件の下、その自宅の敷地は、相続開始直前における被相続人の居住供用宅地等の概念に該当することになる旨が法令に明記されました。
一定の要件とは、次の2つの要件です。
1.被相続人が要介護等認定者に該当(認定申請中に相続開始で事後認定も可)
2.入居老人ホームが老人福祉法等規定該当
都道府県知事への届け出が義務付けられいるため未届状態の老人ホームに入居してしまった場合には、小規模宅地等の特例は受けられなくなります。
無認可老人ホームへの入居は適用除外になりますので、入居時に必ず確認しましょう。
小規模宅地の取得者要件
宅地等の取得者ごとに係る要件もあります。具体的な判定としては、次の各場合には小規模宅地等の特例が使えます。
(1)配偶者が自宅に引続き居住の場合の配偶者が相続
(2)夫婦で老人ホーム入所後、留守宅の自宅を配偶者が相続
(3)被相続人が老人ホームに入所後、引続き居住をする同居親族が相続(生計一は要件ではない)
(4)(2)の物件を(3)の同居親族が相続
(5)(3)の引続き居住の同居親族が対象の自宅を建替えた後に引続き居住継続して相続
(6)被相続人が老人ホームに入所後、留守宅を別居の親族の「家なき子」が相続
なお、(3)の同居親族については、以下の3要件の具備が必要です。
1.相続開始直前に被相続人の居住用敷地に居住している
2.相続税の申告期限まで当該宅地等の所有継続
3.相続税の申告期限まで当該宅地等での居住継続
プラスアルファー
被相続人が老人ホームに入所後の留守宅に生計一親族が入居した場合は、要件不要で適用です。また、留守宅を賃貸した場合、特定居住用宅地等としての特例は使えませんが、貸付事業用宅地としての小規模宅地等の特例を使うことができます(3年以上の期間貸付けが条件)。
2025年6月28日
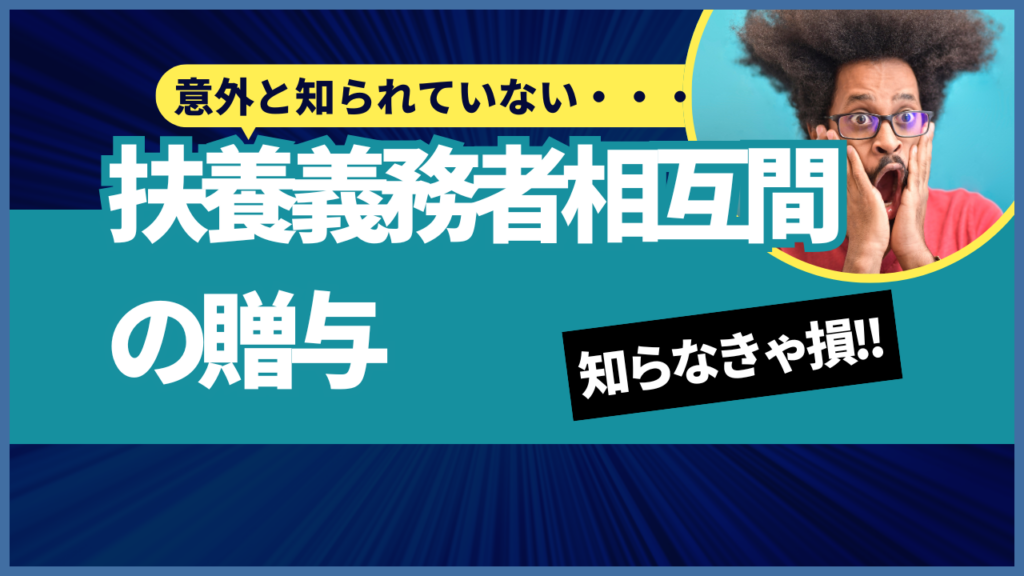
扶養義務者からの生活、教育費の贈与って・・・
新年度がスタートし、入学や進学に伴う学費など、まとまったお金が必要な時期ですね。
令和6年から生前贈与のルールが変わったことで、弊所でも贈与税の相談が増えている現状です。
学費といえば・・・・子・孫への教育資金の一括贈与非課税制度がありますが、
今回はもっとシンプルなお話です。
教育費資金の一括贈与非課税制度が気になる方はこちら
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
1.扶養義務者相互間での生活費または教育費の贈与は非課税。
扶養義務者相互間において生活費、教育費に充てるためした贈与により取得した金銭等で通常必要と認めるものは贈与税の非課税となります。
※要するに必要な時に必要な金額だけもらうということです。
例えば4年間分の大学の学費をまとめて一度に贈与する場合、贈与税の対象となる可能性が出てきます。また、教育費、生活費をもらい実際には使用せず、貯蓄、株式などの取得に充てている場合にも贈与税の課税対象となります。
※まとめて渡すのは要注意!!
毎年必要な都度、必要な金額をお渡ししましょう。(もらいましょう。)
2.生活費・教育費とは
ここでいう、「生活費」とは、通常の日常生活に必要な費用をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるものも含みます。
また、「教育費」とは、教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。修学旅行の費用も含まれます。
3.そもそも扶養義務者って・・・
相続税法に定める扶養義務者は民法上の扶養義務者です。
相続税法第1条の2第1号に定められており、「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
第1条の2《定義》関係|国税庁
「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」
の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A
4.相続税の申告にも・・・・扶養義務者。専門家に相談を
相続税の計算時に、未成年者控除、障害者控除を適用する場面があります。
該当する相続人から控除しきれない部分については扶養義務者から控除できます。
これを知らないと・・・相続税を多く納めてしまう結果に(涙)
経験豊富な専門家である税理士にご相談ください。
2025年4月7日
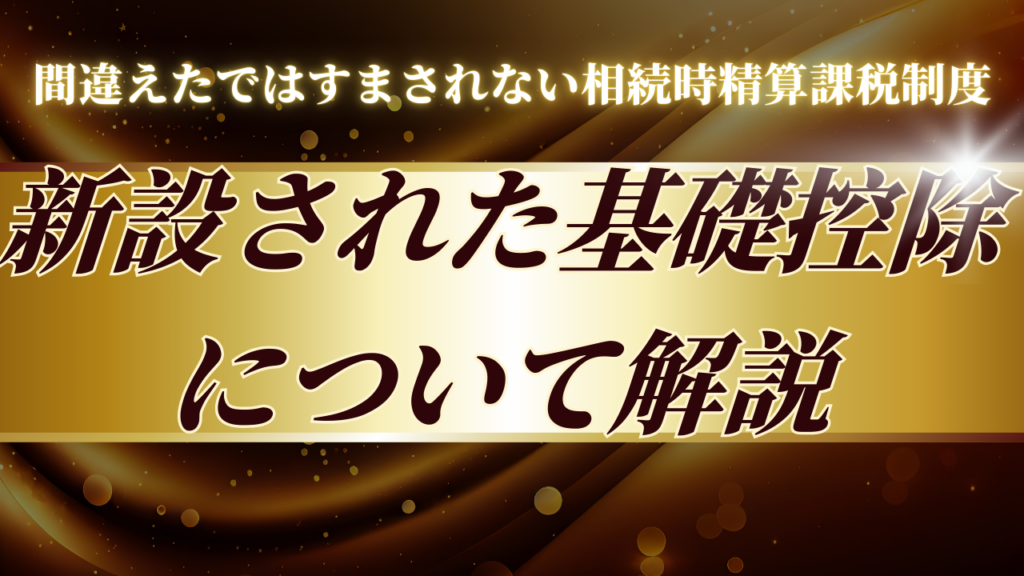
間違えたではすまされない、相続時精算課税制度!!
一度選択したら撤回できない相続時精算課税制度の基礎控除について解説
令和5年税制改正により創設された相続時精算課税制度における基礎控除について解説
大変申し訳ありません。相続時精算課税の概要については割愛しています。
相続時精算課税制度の基礎控除は、令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用されることになります。
■相続時精算課税制度(改正前)
(贈与税の課税価格-特別控除額)×20%
※特別控除額は2,500万円(既にこの規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)
つまり、一生涯で2,500万円です。
この特別控除額は、複数の特定贈与者(財産をあげる人)からの贈与受けた場合には
それぞれ2,500万円あります。
この特別控除額は期限内申告が絶対に必要です。
例えば、父と母の両方と相続時精算課税制度の贈与を選択した場合。
〇 父からの贈与について特別控除額2,500万円
〇 母からの贈与について特別控除額2,500万円
となります。
この考え方があるがゆえに間違えてしまう基礎控除110万円です。
※相続税の課税価格に加算する財産の価額:贈与税の課税価格
■改正の概要
相続時精算課税の適用を受けた贈与に係るその年分の贈与税については、暦年課税(暦年贈与)の基礎控除とは別に、毎年、贈与額から基礎控除110万円を控除できることになります。
計算式
{(贈与税の課税価格-基礎控除)-特別控除額}×20%
※相続税の課税価格に加算する財産の価額:(贈与税の課税価格-基礎控除)
👉ポイント
この基礎控除は、複数の特定贈与者(財産をあげる人)から贈与を受けた場合にはそれぞれの贈与額で按分することになります。
【解説】
例① 祖父、祖母から、暦年贈与によりそれぞれ110万円、合計220万円の贈与受けた場合。
※220万円-110万円(基礎控除)=110万円
110万円に贈与税がかかります。
例② 父から、110万円の暦年贈与、母から相続時精算課税による贈与110万円を受けた場合。
※ 父からの贈与分:110万円-110万円(暦年分の基礎控除)=0
※ 母からの贈与分:110万円-110万円(相続時精算課税の基礎控除)=0
よって、申告不要となります。
母からの贈与について相続時精算課税の初年度の場合、「相続時精算課税選択届出書」を
申告期限までに納税地の所轄税務署へ提出する必要があります。(2年目以降不要)
例③ 父と母からそれぞれ相続時精算課税により110万円の贈与を受けた場合。
(それぞれ初年度の場合)
※ ㋑ 父からの贈与分:110万円-55万円(基礎控除)=55万円
㋺ 55万円-55万円(特別控除額)=0 → 税額は生じませんが申告が必要
〈父からの贈与分に対する基礎控除〉
110万円(基礎控除)×110万円(父〉課税価格)/220万円(父と母の課税価格の合計)
=55万円
※ ㋩ 母からの贈与分:110万円-55万円(基礎控除)=55万円
㊁ 55万円-55万円(特別控除額)=0 → 税額は生じませんが申告が必要
〈母からの贈与分に対する基礎控除〉
110万円(基礎控除)×110万円(母の課税価格)/220万円(父と母の課税価格の合計)
=55万円
※ 父と母からのそれぞれの贈与について初年度ですので「相続時精算課税選択届出書」を
申告期限までに納税地の所轄税務署へ提出する必要があります。(2年目以降不要)
■結論
相続時精算課税制度の基礎控除を理解しないまま選択してしまうと、こんはずではなった
基礎控除110万円となってしまいます。
つまり、申告不要だと思ったのに必要になった。相続税の課税価格に加算される金額が増えてしまった。
申告不要だと思ったのに後日申告が必要となった場合・・・・申告期限後に申告することとなった場合、特別控除額を控除することができないため20%の税率で贈与税が発生します。
相続時精算課税制度を一度選択してしまうと撤回できないため、二度と暦年課税による贈与には戻ってこれらません。要注意です。
2025年2月25日
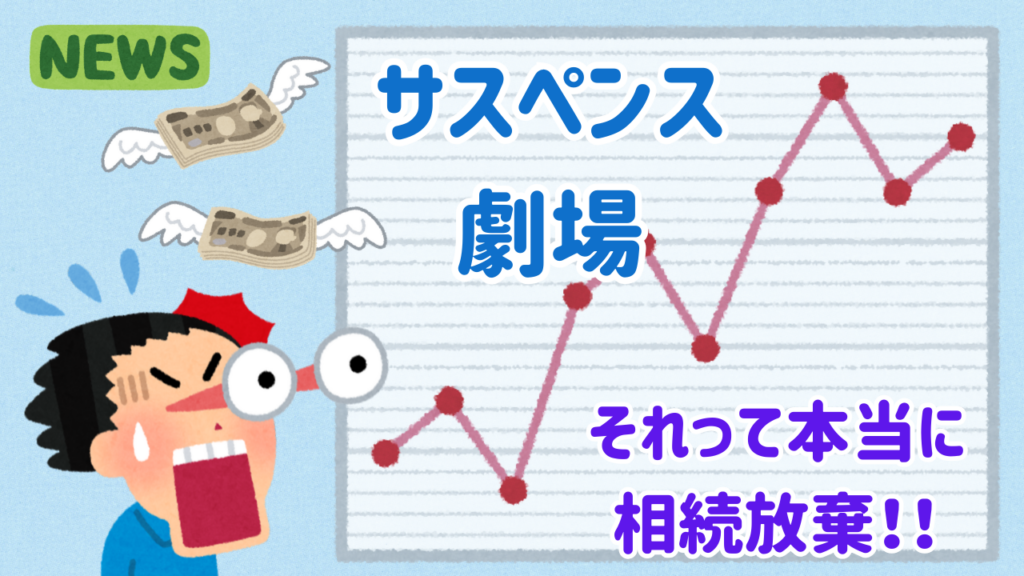
相続放棄の実際の手続きとその流れ
自称サスペンスの帝王は見た~!!
サスペンスの場面ではこんなこと言っていなかった。
サスペンスのワンシーンで出てくる、八百屋の前で会議をしている奥様の会話です。
私は相続放棄したのよ・・・・・。
はんこだけ押してあげたのよ・・・・。
これは、財産をもらわなかっただけで、相続放棄をしたわけではありません。
実際の相続放棄の手続きは次の流れで行います。
相続放棄をすると、遺産分割協議書に押印することはありません。
◆相続における3つの選択
相続が発生すると相続人となる者は、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)、もしくは限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)、または相続放棄(遺産の相続を放棄しプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)のいずれかを選ぶことになります。
相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、借金がなくとも相続にかかわりたくない、財産分与ゼロでハンコを押すのはしゃくだなど、他の理由であっても自分の意思で選べます。
◆相続放棄の手順
(1)家庭裁判所へ相続放棄を申述する
相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならないと定められています。申述書に申述内容を記入し、被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して家庭裁判所に書類を送ります。
(2)家庭裁判所から「照会書」が届く
申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、①誰かに強要されたり、②他人が勝手に手続きしたり、③相続放棄の意味がわからず手続きしていないかなど、その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。
書類をよく読んで、真意である旨を「回答書」に自筆で記載し期限内に返送します。
(3)「相続放棄申述受理通知書」で完了
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)が届いて手続き完了となります。
なお、他の相続人が相続手続きをする際に「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、事前に受理証明書の交付申請を行えば受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。
◆相続放棄のデメリット
相続放棄が完了すると後から撤回できないため、相続放棄完了後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできません。また、他にも個々の事情で発生するデメリットもあり得ます。放棄に際しては、司法書士などの専門家に相談しながら手続きすることをお勧めします。
2025年1月20日

桐生税理士事務所は、秦野市を拠点に「日本一相談しやすい事務所」を目指しています。25年以上の経験を活かし、相続税や法人税、所得税など幅広い税務のサポートを提供。年間4,500件以上の相続税申告実績を持ち、銀行や証券会社での相談経験も豊富です。初回相談は無料で、事前予約により夜間や休日の対応も可能。秦野駅から徒歩10分とアクセスも便利です。神奈川県で税務相談をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。